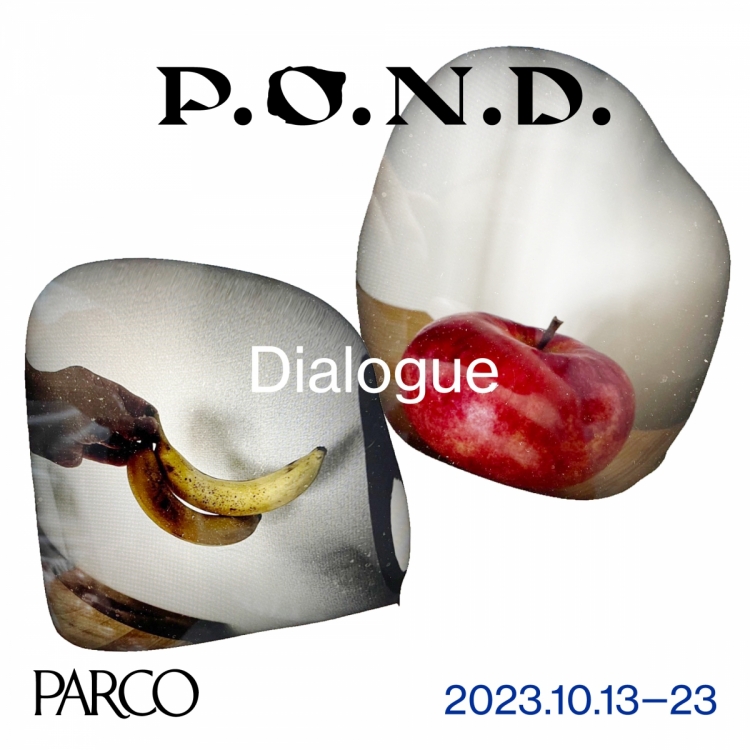2023年10月13日~15日まで、渋谷パルコのGALLERY Xで「GAME:P.O.N.D. ARCADE 2023」が開催された。本記事では、このプログラムの参加レポートをお届けする。
GAME:P.O.N.D. ARCADE 2023とは?
「GAME:P.O.N.D. ARCADE 2023」とは、「P.O.N.D. 2023 Dialogue あたらしい対話に/出会う。」の一環として企画されたプログラムである。

「P.O.N.D. 2023 Dialogue あたらしい対話に/出会う。」とは、アート、ファッション、エンターテインメントなどのさまざまな分野で活躍する新進気鋭のクリエイターによる祭典である。
これは株式会社パルコが主催するイベントで、インディーゲームのプログラム以外には、HIP HOPアーティストによるライブアクト、クリエイターによるトークイベント、シネマショーなどが開催されている。
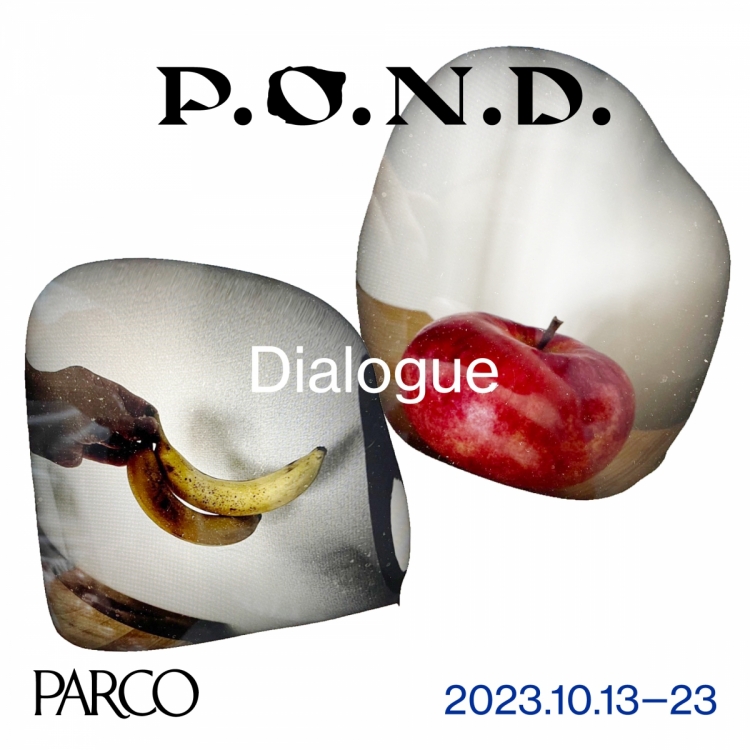
「GAME:P.O.N.D. ARCADE 2023」では、インディーゲームのゲームクリエイター5名によるゲームが試遊できる。本プログラムの監修は、IGN JAPANの今井晋氏。ビデオゲーム本来の姿を取り戻しつつ、人々と現代アートとの対話を試みるもの、とのことだ。
インディーゲームのデモンストレーション
本イベントでは5つのゲームを試遊できた。では、順番に紹介していこう。
『Whale Fall』で最高級の没入感を体験せよ
『Whale Fall』は、海に生きる多種多様な生物になり、海の中を探索するゲームである。

会場では、BENQのプロジェクターで投影されたゲーム画面を見ながら、黄色いソファに座ってプレイができた。この黄色いソファはこのイベントのために特注されたものなのだそう。

プレイヤーは小さな魚になって海の中を進んでいく。普段、私たちが水族館や活魚料理店では左右に泳ぐ魚の姿を横から見ることが多い。しかし、このゲームではプレイヤーの視点は魚の真後ろで、画面の奥に進んでいくイメージだ。
そして、プレイヤーが操作する生物は、小さい魚からイルカへとシームレスに変わっていく。
このゲーム画面には一切UIが表示されない。そのため、映画の世界に入り込んだような気持ちになれる。

筆者は取材で渋谷パルコに来ていることを一瞬忘れてしまいそうになるほど、海の探索に没入してしまった。
その没入感は、魚を後ろから見る視点と繊細な映像美、そして、プロジェクターで投影した巨大なゲーム画面などから来ていると思われる。普段家でプレイしているときはなかなか味わえないものだ。
『Whale Fall』は近日発売予定。興味がある方はウィッシュリストに追加しておこう。

『ルビを振るゲーム』で気づかされた日常にあるアート

続いて紹介する『ルビを振るゲーム』は、文字通り漢字にルビを振っていくブラウザゲームだ。下記リンクから遊ぶことができる。スマートフォンにも対応しているが、PCからのアクセスが推奨とのこと。
プレイヤーはプレイする舞台を上野と渋谷から選べる。筆者は渋谷を選択してみた。

ゲーム画面は、渋谷の風景を切り取られた写真に変わる。渋谷の街にある看板や道路の写真にある漢字にルビを一文字ずつ振っていくのだ。

個人的に、学生の頃ずっと習字と書道をしていた者としては、文字はとりわけ身近な存在である。漢字にルビを振るという行為を通じて、漢字やひらがなの造形の美しさや街にある文字の存在を再認識した。
普段いろんなやるべきことをこなしていく日常の中で、アートが身近なところにあることに意識がいかなかったのだ。

ちょうど筆者がこのゲームをプレイ中に、小学生くらいの子を連れた親子連れがギャラリーに入ってきた。その親子は、「漢字は読める?」とか「ひらがなならわかるかな?」と仲良く会話をしながらこのゲームをプレイしていた。
この親子が渋谷パルコを出た後に、看板の漢字を探しながら「ほら!あそこにも漢字があるよ!」などと笑顔で話している姿を想像し、筆者はあたたかな気持ちになった。
AIの思考を読もう!『デヴィエーションゲーム』
続いては、AIやiPadなど最新技術を活かした、新しいコミュニケーションツールとしてのゲームの可能性を感じさせる『デヴィエーションゲーム』をご紹介しよう。

こちらのゲームは、複数で遊ぶゲームだ。プレイヤーは、ひとりの描き手とひとり以上の回答者に分かれる。描き手は、3つのお題の中からひとつ選び、iPadの画面上にフリーハンドで絵を描いて、そのお題が何なのかを回答者に伝える。
ただし、回答者のひとりはAI。このAIだけにお題がバレないように絵を描かなくてはならない。つまり、AIにお題がバレずに、人間がお題を正解すれば人間の勝ちとなる。

筆者は描き手として3回プレイをしたのだが、3回ともAIにお題がばれずに、人間の回答者にだけお題を伝えることができた。

スタッフの方々によると、3回ともAIに勝ったのは、このイベント開催中で筆者だけだったそう。筆者は今日このゲームに三連勝するために、ウン十年間絵が下手な人生を送ってきたのかもしれない。

冗談はさておき、AIが解析できない絵を描くにはどうすればよいかと筆者は今まで考えたことがなかった。
AIといえば「ChatGPTはスゴイ! もう単純な事務作業はAIに任せよう」と技術の進歩を歓迎する声と、「AIに仕事を取られる! AIはなんだか怖い」とAIがもたらす未来を憂う声が散見している。
一方で、このゲームをプレイした筆者は、「AIはあくまでも技術のひとつなのであって、私たち人間がAIという技術を使いこなせば良い」と感じた。技術は使ってなんぼ。なんのために使うのか、それは人間の倫理観が試されているように思う。私たち自身が真剣に考えていかなければならないことがらであろう。AIに尋ねるのではなく。
この『デヴィエーションゲーム』の発売は、今のところ未定。今後も今回のような展示会でプレイ機会があるかもしれないとのこと。絵でAIに勝つ自信がある方は、ぜひプレイしてみてほしい。
『Dome-King Cabbage』のトリッキーな世界へようこそ
次にプレイしたゲームは『Dome-King Cabbage』だ。

このゲームは、長めのシネマからはじまる。宇宙の世界で何やら起きている模様。積み木を重ねたような不思議な生き物がプレイヤーに話をしてくれるのだが、いまいち要領を得ない。


シネマシーンが終わると、ゲームの選択画面に切り替わる。
ここからは冒頭のシネマとは全く異なる世界観のゲームがはじまる。モンスターを倒していくRPGゲームのようだ。

シネマからRPGの世界に切り替わるのが面白く、純粋に続きが気になるゲームだ。『Dome-King Cabbage』は、近日発売予定。展開がトリッキーなゲームが好きな方は、ウィッシュリストに追加を。

失われた記憶を取り戻す旅へ『OU』
最後に紹介するのは、8月31日に発売されたアドベンチャーゲーム『OU』 だ。

プレイヤーは、記憶をなくした主人公OU(オーユー)。たまに尻尾が燃え上がるネズミのような動物オポッサムのサリーに連れられ、不思議な世界ウクロニアの中を本をめくるように画面の右から左へとゆっくりと進んでいく。

鉛筆のような細い線で描かれた世界がとても美しい。ギャラリーには、ゲームの原画が展示されていた。

ギターが奏でるBGMもどこか懐かしさを感じされる音で、ゲーム全体のやわらかな世界を作り上げている。こちらのBGMもギャラリーで流れていた。

このゲームの面白い点は、そのやさしくてやわらかな世界観を感じるだけのゲームではなく、アドベンチャーゲームとしても楽しめる点だ。
主人公はさまざまな付せんを投げて、いろんなところに貼り付ける。この付せんを投げるのがなかなか一筋縄ではいかない。付せんをゲーム中のさまざまなアイテムに貼り付けて情報を得ると、ゲーム終盤に役立つのだそう。

こちらのゲームは、すでに発売中のゲームだ。サウンドトラックも販売されているので、ぜひ合わせてチェックしてほしい。

ゲームとは何か。私たちがゲームに求めるもの
今回、筆者が「GAME:P.O.N.D. ARCADE 2023」に行って、ゲーミングプロジェクターやAI、タブレットなど最新技術を駆使したゲームのエンターテインメントとしての新しさと、ゲームセンターでプレイする人を少し後ろからみんなで眺めていたあの頃の懐かしさの両方を感じた。
また、アートとしてのゲームの可能性にもワクワクした。アートとはなんぞやという高等な話をするつもりはないが、ゲームという枠組みからさらに飛び出した世界が広がっていることを実感できた。
時折、「ゲームは操作する映画だ」という表現を目にする。たしかに近年のゲームの映像の美しさや脚本の秀逸さは、映画と比べても決して見劣りしない。しかし、ゲームに秘められた可能性はそれに留まることなく、アートの分野でも親和性のあるエンターテイメントであることを、このような素敵なイベントを通してより多くの人に知っていただけたらと思う。