あるゲームジャンルにおいて、ユーザーから高く評価され、その作品抜きには語れないとされるもの。そのビジュアルやゲームシステムが多くのリスペクトを集めるもの。本稿では、そんな"傑作"と称されるインディータイトルを取り上げてご紹介しよう。
『Hyper Light Drifter』は、荒廃しながらもどこか美しさを感じる退廃的な様相のSF世界を、緻密なドット絵で描いた2DアクションRPGだ。アメリカを拠点とするゲーム開発スタジオ"Heart Machine"が手掛ける。
この荒廃した世界にはかつて高度な文明が存在し、今や忘れ去られた知識、失われた技術、埋もれた歴史が人知れず残されている。その身を冒す不治の病の治療法を求めて旅する名も無き放浪者(ドリフター)は、たどり着いたこの地に眠る大きな謎に迫っていくこととなる。


現在ではマルチプラットフォーム展開されているが、当初は2016年3月31日にPC(Steam)にてローンチを迎えた本作。
もともとは、2013年にKickstarterにて開発資金を募るクラウドファンディングを実施し、目標額の$27,000に対して、24,150人の支援者(実は筆者もその1人)から実に約24倍となる$645,158を獲得。

当時の為替レートで約6,400万円という豊富な資金を得たことで、構想段階にあった要素の大部分(※)が詰め込まれ、約2年半の開発期間を経てリリースされた本作はプレイヤーから高く評価された。本稿の執筆時点でのSteamのユーザーレビューは"非常に好評"(13,842件中93%の好評)となっている。
※100万ドルを達成した場合の「SNES(スーパーファミコンベースの海外向け筐体)でのデメイク」のみ実現しなかったが、これは資金が集まりすぎて、もうこれ以外にやることがないということで設けられた要素だった。
治療法を求めて荒廃した世界を旅する
本作のゲームシステムは、画面を俯瞰して見下ろすトップダウン視点のアクションRPG。ストーリー上の目的は治療法の発見となるが、ゲームシナリオの流れとしてはマップ中央にある町を拠点として探索に赴き、東西南北のエリアを攻略。各地でボスを倒し、ある種のキーとなる「モジュール」を起動していく。
探索の舞台となるこの世界は、かつての大戦によって前文明が崩壊してしまっており、今やその大部分が自然に侵食されつつある。だが、その地下には未だに当時のテクノロジーが密かに息づき、侵入者を排除しようとする防衛ロボットや、枷から解き放たれた人造生命体が主人公の行く手を阻むこととなる。

Kickstarterで明かされたコンセプトでは、今作は『ゼルダの伝説 神々のトライフォース』と『Diablo』に影響を受けたとしているが、Heart Machineの創設者であり、リードデザイナーを務めたAlex Preston氏は、後のインタビューにてスタジオジブリ作品(主に『風の谷のナウシカ』)からもインスピレーションを得たと語っている。
終末世界というと何となく暗いイメージがあるかもしれないが、本作で描かれるその様は、退廃的な美というべきものがカラフルな色遣いで表現されている。そこにかつて住んでいた人々、過去に起きた出来事など、大いに想像力を掻き立てられるところに魅力を感じさせるのだ。

そんな本作のもう1つの特徴が、プレイヤーが判読可能な言語的表現が作中に登場しないこと(日本語に対応しているのはオプション項目のみ)。このノンバーバルな手法を用いた著名なタイトルには『GRIS』や『LIMBO』などが挙げられるが、いずれも作中で目撃したものからストーリーを想像するしかない。
その弊害として、次にどこに向かい、何をするべきかという導線のわかりにくさはあるものの、物語の結末までも含めてプレイヤーに想像や考察の余地を残すところに本作の魅力があるのだろう。

電光石火の高難易度アクション
主人公のアクションは、剣と銃を用いた2種類の攻撃手段と、近距離を移動する瞬間的なダッシュによる回避を組み合わせた機動力の高い動きが特徴。剣とダッシュは、各地で見つかる「ギアビット」というある種の通貨と引き換えに、それぞれ3種類のスキルを習得可能だ。
一方で銃はサブウェポンにあたり、探索中に発見することでショットガンなど扱える種類が増えていく。後述するが、本作は接近戦にリスクがあるため遠隔攻撃そのものが有利に働くが、弾数には限りがあり、それを近接攻撃によってチャージするというバランスの取り方がされている。

レベルやステータスの概念はなく、最大HPは5ポイント上限。一度で全快可能な回復薬はあるものの最大所持数は決まっており、先述のとおり防御手段は回避が主体。このため、ヒットアンドアウェイを基本として如何にダメージを受けることなく敵を倒せるかが求められる。
そのプレイフィールは正しく高難易度と言えるもので、ダンジョン攻略の過程もそうだが、特に最深部に待ち受けるボス戦では幾度となく敗北を喫しながらも、その攻撃パターンを覚え、やがて勝利を掴むまで繰り返し挑むこととなるだろう。

本稿を執筆している2025年の今でこそ、こうした硬派なスタイルは高難易度2Dアクションのスタンダードとして用いられることも多いが、当時としてはこの一見シンプルながら、だからこそプレイヤー自身の腕が問われるようなスタイルに新鮮さを感じたものだ。
主人公の動きと敵のモーションのバランスとの取り方が秀逸で、戦いに敗れてしまったとしても理不尽さを感じさせることなく、自分が上手く動けなかったのだと思わせるような説得力がある。

主人公は病に冒されてはいるが、その剣筋は最後まで衰えることはない。だが、激しい戦闘を終えた後に少しよろめき、吐血の痕を地面に残しながらも体勢を立て直して再び歩みだすその姿に、破滅的な格好良さを感じてしまうのはきっと筆者だけではないと思うが――いかがだろうか。
厳密には本作がオリジンというわけではないが、ビジュアルやゲームシステムなど、本作へのリスペクトを感じさせる作品は後に続いている。後発作品の中には本作をより洗練したと感じるものもあるが、今日でも多くのタイトルの中に、本作が与えたであろう影響の大きさを感じるのだ。
『Hyper Light』シリーズ新作はもうすぐ
Heart Machineが手掛けるシリーズ最新作として、本作と世界観を同じくする『Hyper Light Breaker』のローンチが2025年1月15日に迫っている。早期アクセスでのリリースとなり、特徴的な色遣いに『Hyper Light Drifter』の名残りを感じさせるが、ゲームデザインは2Dから3Dへと移行。オープンワールドを舞台に、最大3人までのオンラインマルチプレイにも対応している。
時間軸としては『Hyper Light Drifter』よりも前の時代が舞台になるとされており、ファンにとっては約8年ぶりのシリーズ最新作となるわけだ。


しかし、高まる期待に対してHeart Machineは混乱の最中にあるようだ。
詳細な経緯は省くが、昨年巻き起こったTake-Two InteractiveによるGearbox Entertainmentの買収劇により、同作のパブリッシング権を持つレーベル"Gearbox Publishing"は現在の"Arc Games"に改名。
こうした事態を受け、Heart Machineは進行中の開発体制には影響はないと表明していたものの、実際にはその余波を受ける形でリリースに数ヶ月の遅れが生じ、同年11月にはスタジオ関係者のレイオフ(人員削減)があったことも報じられている。
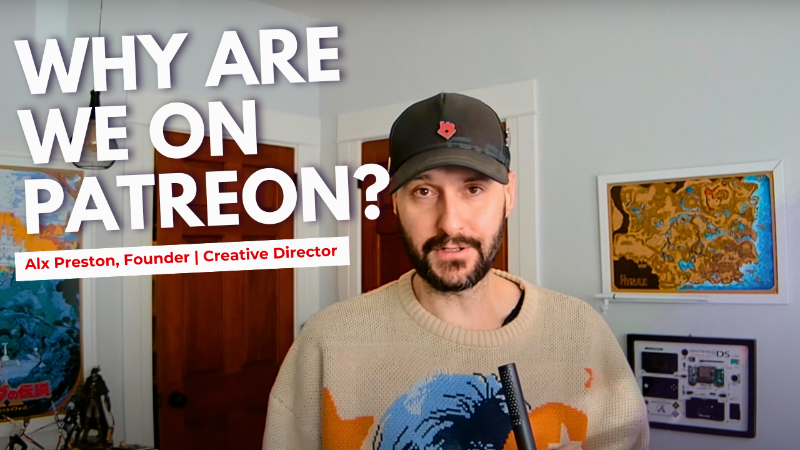
そんな状況にあって、2024年12月25日にAlex Preston氏はYouTubeにてビデオメッセージを公開し、業界を取り巻く状況を伝えた上で、今後もスタジオを安定的に存続させていく1つの手段として、Patreon(ファンとクリエイターをつなぐ月額会員制のプラットフォーム)にてメンバーシッププログラムを開始したことを表明している。
本稿ではあくまでその事実を伝えるのみとさせていただくが、ローンチを間近に控えた『Hyper Light』シリーズ最新作が、ファンの期待に応えてくれるものとなってくれることを願ってやまない。
| 基本情報 | Hyper Light Drifter (ハイパーライトドリフター) |
|---|---|
| 開発 | Heart Machine Abylight Studios(移植) |
| 販売 | Heart Machine Abylight Studios PLAYISM |
| 言語 | 日本語有り(Xbox以外) |
| 配信日 | 2016年3月31日 / Steam |
| 2016年7月26日 / Xbox One, Xbox Series X/S | |
| 2017年5月25日 / PlayStation 4 | |
| 2018年9月6日 / Nintendo Switch | |
| 2019年7月25日 / iOS | |
| 2024年6月17日 / Android | |
| 定価 | 1,980円(Steam) |
| $19.99(Xbox One, Xbox Series X/S)※海外ストア | |
| 2,480円(PlayStation 4) | |
| 2,500円(Nintendo Switch) | |
| 800円(iOS) | |
| 820円(Android) |



